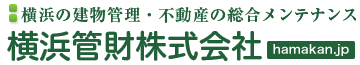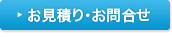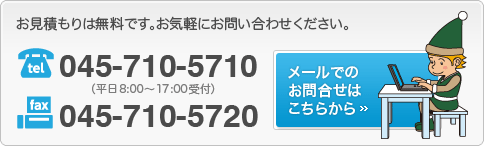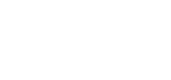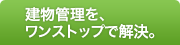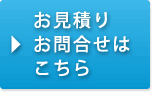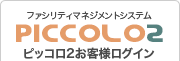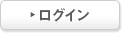水質検査
水道法により「給水栓(蛇口)における水の色、濁り、におい、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、必要な水質検査をすること」とあります。
又、特定建築物においてはビル管法により水質検査は必須事項となっています。
作業対象
- 水質検査10項目(省略不可項目)
- 水質検査5項目(重金属及び蒸発残留物)
- 消毒副生成物12項目
- レジオネラ菌検査
- 残留塩素測定
検査内容
水質検査(10項目、5項目、12項目)
貯水槽清掃後、給水系配管の末端からサンプルを採取し、認可を受けた検査機関に提出。
その結果により報告書を作成いたします。
レジオネラ菌検査
冷却塔、浴槽、シャワー等から定期的にサンプルを採取し、認可を受けた検査機関に提出。
その結果により報告書を作成いたします。
検査の頻度は建物の用途により異なります。
残留塩素測定
残留塩素測定器を用いて遊離残留塩素の濃度を測定します。
検査の基準
- 塩化物イオン mg/l 200以下
- 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/l 10以下
- 有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/l 5以下
- 一般細菌 /ml 100以下
- 大腸菌 /ml 検出されないこと
- pH値(21℃) - 5.8以上8.6以下
- 臭気 - 異常でないこと
- 味 - 異常でないこと
- 色度 度 5以下
- 濁度 度 2以下
- 亜鉛及びその化合物 mg/l 1.0以下
- 鉄及びその化合物 mg/l 0.3以下
- 銅及びその化合物 mg/l 1.0以下
- 鉛及びその化合物 mg/l 0.01以下
- 蒸発残留物 mg/l 500以下
計測事例